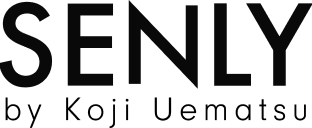LIFESTYLE
江戸の粋に学ぶ淑女のお作法 ♯4

「江戸の粋に学ぶ淑女のお作法」連載4回目のテーマは「言葉遣い」です。現代社会でも役立つ江戸時代のコミュニケーション術を「えどのいき」を発信している前田さんにお聞きしました。
植松氏(以下敬称略)
江戸って、参勤交代やご商売などで全国から訪れた人々で賑わっていた町。それだけに独自の粋なコミュニケーション術が発達したんですね。
前田氏(以下敬称略)
そうなんです。多くの人との出会いを楽しめるのも江戸ならでは。とはいえ商人の町でもあったので、どんな人にも失礼のない言葉遣いが重んじられていました。そこで今回は現代の人付き合いにも役立つ言葉遣いの心遣いをいくつかご紹介します。
言霊は自分に返ってくるもの
コミュニケーションにおいて言葉は最も大切な要素です。商人たちはどんな人にも失礼のない言葉遣いを重んじました。例えば、店主は従業員に対しても「おはようございます」と丁寧語で挨拶をし、頼みごとをするときは「~してくれないかい?」といったように対等に依頼しました。威張らないのが粋なのです。
三脱の教え
初対面の人に職業、年齢、地位を聞かないという教えがありました。相手の本質を重んじるということです。はじめはぞんざいな話し方をしていたのに、相手の職業や立場を知ったとたんに「そんな偉い方とは存じませんで…」など手のひら返しで態度を変えるのは野暮というもの。
植松
誰とお話しするときでも最初から丁寧な言葉遣いを心がければよいのですね。
前田
そうですね。人との出会いに感謝するのも江戸の粋のひとつです。
目の前の人を仏の化身と考える
人との出会いは仏様が導いてくれたもの。だからコミュニケーションはすべての人をリスペクトすることが大切です。
植松
嫌なことがあっても「すべて仏様からの贈り物」って一拍おくようにすると、ムダに怒ることもなくなるかも。「この人に会えたから、良くなったこともある」っていいことだけピックアップすると自分自身が幸せになるかもしれませんね。
前田
そうなんです。人生っていろいろなことがあってこそ今の自分があるのですから。
あと、「すみません」は心が「澄んで」いないということ。「すいません」ではありません。お礼を言うときは「すみません、助かりました。ありがとうございました」まで惜しみなく言葉を伝えましょう。
また、「粋」ではない話し方に対してのいくつかの言葉もご紹介します。
半畳を入れる
江戸時代に、歌舞伎や芝居小屋などで気に入らない役者がいると、自分が敷いていた半畳分のゴザなどを投げ入れたことを言います。それを由来に、人の話に割って入ってその場の雰囲気を壊すようなことを「半畳を入れる」と言ったそうです。
植松
話しをしている最中に、突然「それでね」っていきなり違う話に持って行っちゃう人もいますよね。それはもう、半畳を入れるというより一畳投げるっていう感じですね!
前田
その場の雰囲気を壊す人って気遣いが足りない人が多いですよね。江戸時代にもそういう人は当然いたみたいで、せっかく話が弾んでいるところに否定的な言葉で場の空気をしらけさせるのが「水掛け言葉」、「だって~」や「でも~」などと話を遮るのを「戸締め言葉」、「だから?」「それで?」など脅すような言い方を「手斧(ちょうな)言葉」と言います。
植松
本当にいろいろな言い方があるんですね。覚えておくと普段の会話にも活かせそう。
前田
あと、「お気の毒に」という言葉は今でもよく使いますが、そんな気の毒な人を気遣って楽になるような言葉をかけてあげることを「気の薬」と言うんです。
「何かあれば手伝うから言ってね」と声を掛けられるだけで、実際になにもしてもらわなくても気が楽になるもの。
そして「お忙しそうですね、お疲れ様です」っていう言い回しもありがちですが、「ご活躍ですね、素敵です」って言い換えてみてください。なんだかお互いいい気分になりそうじゃありませんか?
植松
SNSやメールでやり取りすることが増えた今、言葉の使い方がさらに難しくなっている気がします。気遣いのある言葉選びで粋にコミュニケーションがとれるようになりそうですね。
【PROFILE】
前田眞里さん/CAとして日本航空に勤務後、結婚、子育てを経て「自分のための化粧品を作りたい」と16年前に株式会社ジュエルジャパンを設立。NPO法人江戸〇ぐさ元理事、女性の学びの場、「青山なでしこ学院」創立メンバー。noteにて「えどのいき」を発信中。
https://note.com/legit_hawk1794
https://www.jeweljapan.jp/
text:AYAKO TAKAHASHI