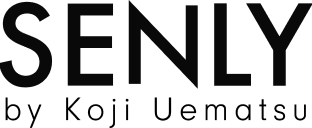LIFESTYLE
江戸の粋に学ぶ淑女のお作法 ♯3

「江戸の粋に学ぶ淑女のお作法」連載3回目のテーマは「気配り」についてです。現代社会でも役立つ江戸時代のコミュニケーション術を「えどのいき」を発信している前田さんにお聞きしました。
前田氏(以下敬称略)
今回は現在の都会同様、人混みであふれていた江戸の町での「気配り」についてご紹介しますね。
自分の気持ちもラクになる
~うかつあやまり~
前田
例えば、足を踏んだり踏まれたりって、私たちの普段の生活でもよくあることですよね。江戸の町では、足を踏まれたら、踏んだ方はもちろん謝りますが、そのときに「こんなところに足を出していた私もうかつでした」という眼差しを返すのが「うかつあやまり」です。
植松
電車の中とか特に足を踏まれるってありそうですね。その時に相手にムカッとするんじゃなくて「こちらこそうかつでした」という対応をするっていうことですね。
前田
物事には100パーセント相手が悪いということは少なくて、実は自分もうかつだったなと思うことがありますよね。足を踏まれて「痛っ!」とビックリした後に、咄嗟にそんな粋なしぐさができたら素晴らしいことではないかしら。
「うかつあやまり」は仕事やクレーム処理、接客などのアンガーマネジメントにも繋がるのです。何かトラブルが起きた際、ミスした相手を頭ごなしに怒るのではなく「私も念を押せばよかったわ」「こちらの説明が足りなかったわね」などと言えることで、自分の気持ちもラクになるんです。
植松
すごい、大人の対応! 相手を責めるだけじゃなくて、自分のうかつさに目を向けることが逆に自分の気楽さにつながるのですね。
思いやりこそが江戸の粋
~江戸っ子~
植松
よく「私って江戸っ子なの」とかいう人がいますよね? 実際江戸っ子の定義ってあるんですか?
前田
よく「三代続くと江戸っ子」と言われますが、江戸時代中期以降はほとんどの人が地方からの移住者でした。文献として「江戸っ子」の記述が見られるのは1700年代後半で、江戸の町も栄えてからのことなのです。
江戸では、寺子屋だったり教養のある商人のリーダー達が人生哲学を教えていました。
たくさんの人達がひしめき合う江戸で、みんながトラブルなく生活できるような、思いやりの文化が「江戸っ子とはこうあるべき」という意識を芽生えさせていったと思われます。
江戸○ぐさに登場する江戸っ子は、地方から来て江戸の流儀を知らない人がいたら、江戸っ子じゃないなと思って仲間外れにするのではなく、仲間に入れて教えてあげていたんです。
植松
知らない街や知らない人達の中に入るのは容易なことではないですよね。でも「江戸っ子なら仲間外れにするなんて粋じゃない!」となれば、外から来た人たちも過ごしやすい街だったんでしょうね。
現代の都会はあまりにも多くの人がいるから、違った意味で人間関係がドライで過ごしやすい面もあるけど、江戸っ子気風のある下町も人情味があふれていて住みやすそうですね!
【PROFILE】
前田眞里さん/CAとして日本航空に勤務後、結婚、子育てを経て「自分のための化粧品を作りたい」と16年前に株式会社ジュエルジャパンを設立。NPO法人江戸〇ぐさ元理事、女性の学びの場、「青山なでしこ学院」創立メンバー。noteにて「えどのいき」を発信中。
https://note.com/legit_hawk1794
https://www.jeweljapan.jp/
text:AYAKO TAKAHASHI